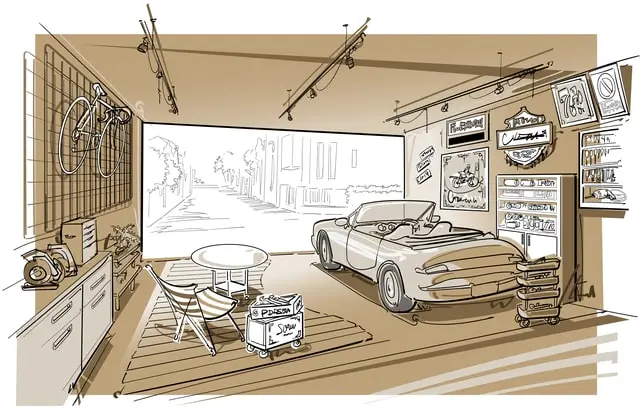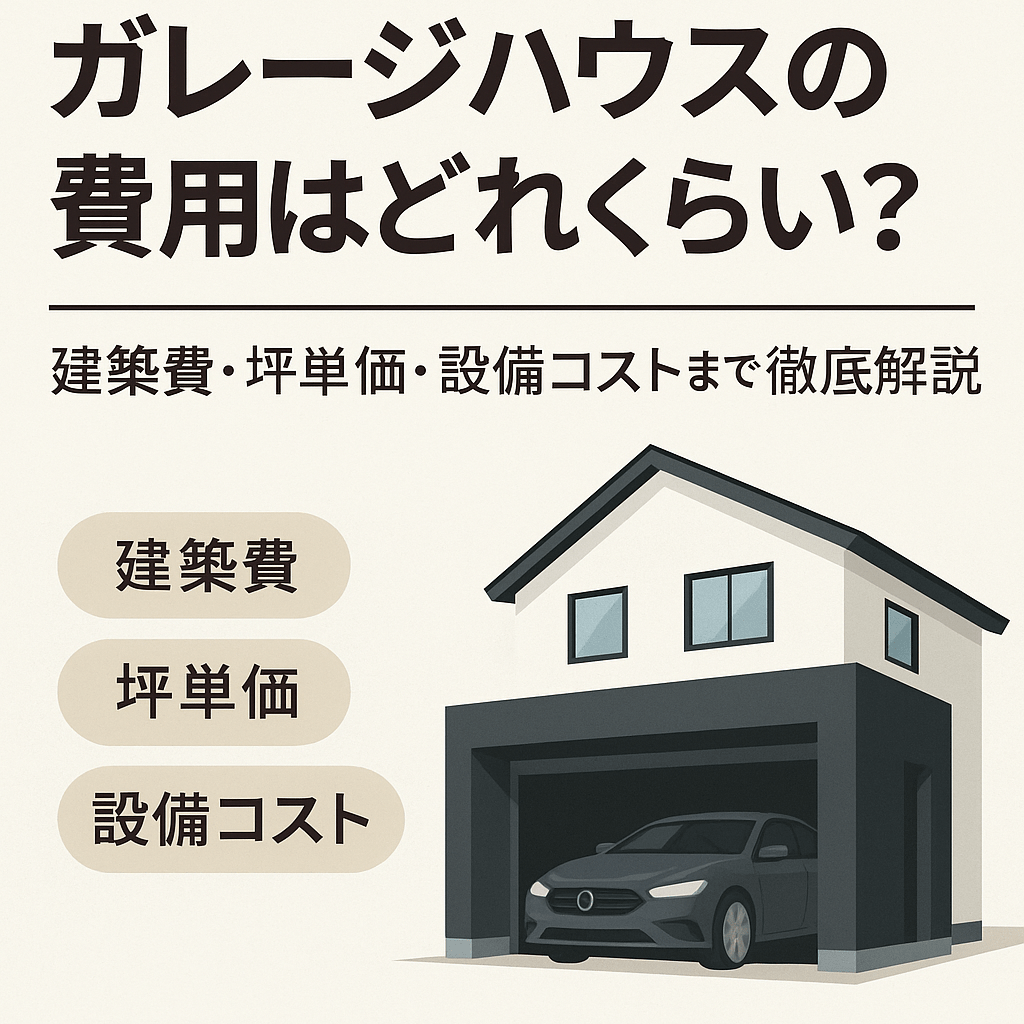
住宅ローンを検討するときに、多くの人が最初に悩むのが「変動金利にするか、固定金利にするか」 という選択です。
近年は金利上昇のニュースも増え、「長期的に金利が上がるのでは?」という不安から、金利を固定できる『フラット35』 に注目が集まっています。フラット35は、返済期間中の金利がずっと変わらない“全期間固定金利”の住宅ローンで、将来の金利変動に左右されずに安心して返済を続けられるのが特徴です。
しかしその一方で、
- 「変動金利よりも初期金利が高い」
- 「借り換えや審査条件が複雑そう」
といったイメージを持つ人も多く、実際のメリット・デメリットを正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、フラット35の金利推移・特徴・メリット・デメリットを徹底解説し、さらに他の住宅ローンとの違いも比較します。
この記事を読んだ後には、「自分にはフラット35が合っているのか?」「変動金利の方が良いのか?」という判断がスッキリできるはずです。
フラット35とは?基本の仕組みを解説
「フラット35」は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している全期間固定金利型の住宅ローンです。
最大の特徴は、借入時に決定した金利が返済が終わるまで一切変わらないこと。そのため、将来の金利変動を気にせず、長期的に安定した返済計画を立てたい人に選ばれています。
変動金利のように半年ごとに金利が見直されることもなく、「毎月いくら返すのか」が借入時点で確定するため、家計管理がしやすい点も大きな魅力です。
全期間固定金利の住宅ローン
フラット35は、名前のとおり最長35年間、金利が固定される住宅ローンです。
一般的な固定金利型ローンの中には「10年固定」「20年固定」などの期間限定タイプもありますが、フラット35は返済期間すべてが固定金利となります。
そのため、仮に将来金利が上昇しても、毎月の返済額が変わらないという安心感があります。
逆に、金利が下がった場合でも返済額はそのままですが、「金利上昇リスクを避けたい」「長期的な安定を重視したい」という人にとっては非常にメリットの大きい選択肢です。
また、金利は借入時のタイミングで決まるため、「いつ申し込むか」「どの金融機関を選ぶか」によっても適用金利が変わります。住宅購入を検討する際は、最新の金利情報を確認しておくことが重要です。
利用できる人・条件・借入限度額
フラット35は、原則として自分が居住する住宅の購入・新築・建て替えを目的とした人が対象です。投資用物件やセカンドハウスなど、自己居住以外の目的では利用できません。
また、借入条件には以下のような基準があります。
- 年収に対して返済比率が一定以下であること(年収400万円未満の場合30%以下、400万円以上の場合35%以下)
- 住宅の建設費または購入価格が1億円以下であること
- 借入期間は15年以上35年以下であること(※建物の耐久性によって異なる)
- 対象住宅が、住宅金融支援機構が定める技術基準を満たしていること
借入限度額は、原則として8,000万円以内(土地+建物を含む)ですが、借入金額は物件価格と年収に応じて決まります。
これらの条件を満たすことで、誰でも利用できるのがフラット35の特徴です。
民間金融機関と住宅金融支援機構の共同運営
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)が連携して運営しています。仕組みとしては、銀行や信用金庫などの民間金融機関が利用者に資金を貸し出し、そのローンを住宅金融支援機構が買い取ることで成り立っています。
これにより、金融機関側はリスクを軽減しつつ、利用者は長期固定金利という安定したローンを利用できるという“双方にメリットのある制度”となっています。
また、機構が一括で資金を調達することで、民間よりも低めの固定金利を実現している点も特徴のひとつです。
この公的機関が関与する仕組みがあるからこそ、フラット35は「信頼性が高く、安心して利用できる住宅ローン」として長年支持され続けています。
フラット35の金利推移 ― 過去から現在までの流れ
フラット35は、「長期固定金利型住宅ローン」として、景気や政策金利の影響を比較的受けにくい安定した金利が特徴です。しかし、完全に一定ではなく、市場の長期金利(=国債利回り)の動きに連動して少しずつ変化しています。
ここでは、直近の金利推移と今後の動向、さらに変動金利や他の固定金利商品との違いを整理していきましょう。
直近5年の金利推移と傾向
フラット35の金利は、過去10年以上にわたり「歴史的な低水準」で推移してきました。以下は、おおよその過去5年間の金利推移(融資率9割以下・借入期間21年以上)をまとめたものです。
| 年月 | フラット35(実効金利) |
|---|---|
| 2019年 | 約1.30%〜1.40% |
| 2020年 | 約1.25%〜1.35% |
| 2021年 | 約1.30%〜1.40% |
| 2022年 | 約1.40%〜1.50% |
| 2023年 | 約1.60%〜1.80% |
| 2024年 | 約1.80%〜1.90%台で推移 |
このように、2023年以降はやや上昇傾向にあり、背景には日本銀行による金融緩和政策の調整や、世界的なインフレの影響があります。
それでも、2%未満の水準にとどまっており、過去に比べれば依然として「低金利状態」が続いているといえます。
長期的に見れば、フラット35の金利は「安定性重視のローン」として、短期間で大きく変動することは少ない傾向にあります。
今後の金利動向予測(2025年時点)
2025年現在、フラット35の金利はおおむね年1.8〜2.0%前後で推移しています。
日銀の金融政策転換により、長期金利がやや上昇基調にあるため、今後も小幅な上昇が続く可能性があります。
ただし、急激な上昇は考えにくく、安定的に2%前後で推移するというのが多くの専門家の見方です。景気が落ち着けば再び横ばい、あるいは微減する可能性もあるため、「金利が大きく変わる局面ではない」という点は安心材料といえるでしょう。
また、金利上昇が懸念される局面では、「今の金利で固定しておく」というフラット35のメリットがより際立ちます。
変動金利と違い、将来の上昇リスクを受けないため、“長期的な安定”を重視する人には引き続き有利な選択肢といえます。
関連記事:変動金利のリスクとは?知らないと危険な金利上昇シナリオを徹底解説
変動金利・他の固定金利商品との比較
フラット35と他の住宅ローンの違いを理解するには、金利タイプごとの特徴を比較するのが効果的です。
| 金利タイプ | 金利水準(2025年) | 特徴 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 約0.4〜0.7% | 初期金利が低いが、将来的に上昇リスクあり |
| 固定期間選択型(10年固定など) | 約1.0〜1.5% | 固定期間終了後に金利見直しあり |
| フラット35(全期間固定) | 約1.8〜2.0% | 借入から完済まで金利が変わらない安心感 |
このように、フラット35は他のローンよりも金利水準はやや高いものの、返済額が一定で安心して長期計画を立てられるのが強みです。
特に、「今後金利が上がる可能性がある」と考える人にとっては、変動金利よりもリスクを抑えられる選択肢といえるでしょう。
一方で、短期的に売却や住み替えを予定している人、または繰上げ返済を早く進める予定の人にとっては、変動金利の方が総返済額を抑えられるケースもあります。つまり、フラット35は「長く安心して住む家を持ちたい人」に向いた住宅ローンなのです。
関連記事:固定金利と変動金利、どっちが得?住宅ローン金利比較について
フラット35のメリット
フラット35は、他の住宅ローンと比べて金利がやや高めに設定されているものの、それ以上に「長期的な安心と安定」を得られる点が大きな魅力です。
金利変動のリスクを避けたい人や、将来のライフプランを見据えて計画的に返済したい人にとって、フラット35は信頼性の高い選択肢といえます。
ここでは、代表的な3つのメリットを紹介します。
金利が固定されている安心感
フラット35最大の特徴であり、最大のメリットは、「全期間固定金利」であることです。借入時に金利が確定し、完済まで金利が変わらないため、将来の金利上昇に左右されることがありません。
たとえば、変動金利で3,000万円を借りた場合、金利が1%上がると総返済額が600〜700万円増える可能性があります。
しかしフラット35なら、契約時の金利が固定されているため、返済額が35年間ずっと一定です。家計の見通しが立てやすく、「毎月の返済が急に増える」心配がないのは大きな安心材料です。
特に、子育てや教育費など今後の支出が読みにくい世帯や、将来の収入変動に備えたい人にはぴったりの住宅ローンです。
繰上げ返済の手数料が無料
一般的な住宅ローンでは、繰上げ返済を行う際に手数料が数千円〜数万円かかるケースがあります。しかし、フラット35では繰上げ返済の手数料が無料で、しかもネット上から簡単に手続きできるという大きな利点があります。
たとえば、ボーナスや臨時収入があった際に、無理のない範囲で元本を減らすことが可能です。元本を早めに減らせば、その分利息も減り、総返済額を数十万円単位で抑えることができます。
また、手数料が無料ということは「少額でも繰上げ返済しやすい」ということ。
まとまったお金がなくても、10万円単位からコツコツと返済を進めることで、将来的な返済負担を大幅に軽減できます。
団体信用生命保険(団信)の選択肢が広い
住宅ローンの返済期間中に、もしものこと(死亡や高度障害)があった場合、残りのローンが完済される仕組みが団体信用生命保険(団信)です。
フラット35では、この団信の加入・未加入を自由に選べるだけでなく、保障内容の選択肢が豊富なのも特徴です。
たとえば、がん・急性心筋梗塞・脳卒中などの「3大疾病付き」や、「介護保障付き」など、自分や家族のライフスタイルに合わせて保険内容を選べます。
また、団信に加入しないことで保険料分のコストを削減することもできるため、柔軟な設計が可能です。
多くの民間ローンでは団信加入が義務付けられていますが、フラット35は「必要な保障を自分で選べる」点で優れており、保険面でも安心と自由を両立できます。
フラット35のデメリット
フラット35は、長期にわたって金利が固定される安心感が魅力の住宅ローンですが、当然ながらメリットだけではありません。安定性の代わりに「初期金利が高い」「審査がやや厳しい」といった注意点も存在します。
ここでは、フラット35を検討する際に知っておくべき3つのデメリットを解説します。
変動金利に比べて初期金利が高い
最も大きなデメリットは、変動金利よりも初期金利が高いことです。2025年現在の金利を比較すると、変動金利は年0.4〜0.7%程度であるのに対し、フラット35は年1.8〜2.0%前後が一般的です。
たとえば3,000万円を35年ローンで借りた場合、変動金利0.5%なら月々の返済額は約7.6万円ですが、フラット35(1.8%)では約9.6万円となり、月々2万円・総額で約800万円の差が生じます。
この差は、「金利上昇リスクを回避するための安心料」ともいえますが、短期間で完済予定の人や、今後繰上げ返済を積極的に行う人にとっては、やや割高に感じるかもしれません。
長期的に見ると安定性というメリットが勝ちますが、「短期的なコスト」には注意が必要です。
審査基準がやや厳しく、融資まで時間がかかる
フラット35は公的要素の強い住宅ローンであるため、審査基準が民間の銀行ローンよりもやや厳しい傾向があります。
たとえば、借入対象の住宅が「住宅金融支援機構が定める技術基準」を満たしている必要があり、耐震性・断熱性・省エネ性能などが基準に達していないと融資が受けられません。
また、審査は金融機関と住宅金融支援機構の双方で行われるため、融資実行までに時間がかかることもあります。
一般的な銀行ローンが1〜2週間程度で審査が完了するのに対し、フラット35では3〜4週間程度かかるケースもあります。
そのため、「すぐに契約・決済を進めたい」という場合には不向きな面もあります。
住宅購入のスケジュールを立てる際には、フラット35の審査期間も考慮して余裕を持って進めることが大切です。
借入当初に必要な諸費用が高くなるケースも
フラット35では、借入時に必要な諸費用が比較的高くなる場合があります。特に、団体信用生命保険(団信)の保険料が別途必要になる点が、民間ローンとの大きな違いです。
民間の住宅ローンでは団信が金利に含まれているケースが多いのに対し、フラット35では団信の加入が任意であり、加入する場合は別途保険料がかかります。(例:3,000万円の借入で年間数万円〜十数万円程度)
また、固定金利のために金利が高めに設定されていることから、借入額が多い人ほど当初の支払い負担が大きくなる傾向にあります。
さらに、融資手数料や登記費用、保証料なども金融機関によって異なるため、事前に見積もりを比較しておくことが重要です。
これらの初期費用を含めてトータルコストを把握しておかないと、「思っていたよりも支払いが重い」という状況に陥ることもあります。
フラット35はどんな人に向いている?
フラット35は「全期間固定金利」という特性から、すべての人に最適な住宅ローンというわけではありません。
短期で返済を終える人や、収入に余裕がなく金利の低さを優先したい人にとっては、変動金利のほうがメリットが大きい場合もあります。
しかし、長期的な安定を重視する人にとっては、フラット35は非常に魅力的な選択肢になります。
ここでは、どんなタイプの人に向いているのかを3つの観点から解説します。
安定収入があり、長期的に同じ家に住む予定のある人
まず、フラット35が最も適しているのは、安定した収入があり、同じ家に長く住む予定のある人です。
フラット35は35年間という長期の返済期間を前提としており、金利が固定されているため、長く住めば住むほどそのメリットを享受できます。
たとえば、転勤の多い職種や数年後に売却・住み替えを検討している場合、フラット35の「長期固定金利」の恩恵は十分に得られません。
一方で、安定した勤務先で継続的な収入が見込める人や、マイホームを終の棲家にするつもりの人にとっては、将来にわたって返済額が変わらない安心感が大きな魅力となります。
つまり、「これからの暮らしを安定させたい」「家族と長く住む家を持ちたい」という人にこそ、フラット35はおすすめのローンです。
将来の金利上昇リスクを避けたい人
次に、「金利が上がったらどうしよう」という不安を感じている人にも、フラット35は適しています。
変動金利型のローンは、景気や政策金利の変化に応じて半年ごとに見直されるため、将来的に金利が上昇すれば返済額が増えるリスクがあります。
その一方で、フラット35は借入時の金利が完済まで固定されるため、将来の経済状況に影響されません。
金利が2%上がっても、毎月の返済額は一切変わらないため、家計が急に圧迫される心配がありません。
この「安心感」を得るために、多少初期金利が高くてもフラット35を選ぶ人は多く、特に「安定した支出を好むタイプ」や「リスクを避けたい人」に向いています。
不確実な時代だからこそ、フラット35のような安定型ローンは大きな価値を持つのです。
家計の計画性を重視したい人
最後に、家計のバランスを重視して計画的に暮らしたい人にも、フラット35は適しています。
固定金利のため、毎月の返済額が一定で予測可能なことから、教育費・生活費・貯蓄などの支出計画を立てやすくなります。
たとえば、子どもの進学や老後資金など、今後のライフイベントに合わせて長期的な家計プランを立てる際、返済額が一定であることは非常に大きなメリットです。
また、金利変動によるストレスがないため、精神的にも安定して家計管理を続けられます。
「家計を可視化し、将来の安心を確保したい」「堅実に返済を続けたい」という考えの人にとって、フラット35は理想的な選択肢といえるでしょう。
フラット35と他の住宅ローンを比較
住宅ローンには「変動金利」「固定期間選択型」「全期間固定(フラット35)」の3つが代表的なタイプとして存在します。それぞれにメリットとリスクがあり、「どれが一番お得か」は人によって異なります。
ここでは、フラット35を軸に、他の住宅ローンと比較しながら特徴と向き・不向きを解説します。
変動金利との違い(リスクと安定性)
まず、最も多くの人が利用している変動金利型との違いを見てみましょう。変動金利は、借入当初の金利が非常に低く、2025年時点では0.4〜0.7%前後が主流です。一方、フラット35は1.8〜2.0%前後と約1%以上の差があります。
そのため、変動金利のほうが初期の返済負担は軽く、総返済額も少なく見えるのが特徴です。しかし、金利が上昇した場合には返済額も増加するため、長期的なリスクを抱えています。
たとえば、金利が1%上昇すると、3,000万円の35年ローンで総返済額は約600万円も増加します。
つまり、「今は得だけど、将来リスクがある」のが変動金利。対してフラット35は、「今は割高だが、将来の変化に強い」ローンです。
安定を求めるならフラット35、低金利を活かしたいなら変動金利――このように目的によって選び方が変わります。
固定期間選択型ローンとの違い
次に、固定期間選択型ローン(例:10年固定、20年固定など)との違いです。このタイプは、一定期間(5年・10年・20年など)金利が固定され、その期間終了後は変動金利または再設定された固定金利に切り替わる仕組みです。
一見、フラット35と同じように「固定金利で安心」と思われがちですが、固定期間終了後の金利が読めないという不確実性があります。
特に、固定期間終了時に市場金利が上昇していると、返済額が大幅に増えるリスクがあります。
たとえば、10年固定ローンで金利1.0%だったものが、10年後に2.0%に上がった場合、返済額は約15〜20%も増加します。対してフラット35は、借入時に決まった金利が完済まで変わらないため、将来の変動リスクが一切ありません。
つまり、短期的な金利の低さを重視するなら固定期間選択型、長期の安心を重視するならフラット35が適しています。
借り換えのタイミングとメリット
フラット35は、借り換えによる金利引き下げや総返済額の削減も可能です。たとえば、過去に金利2.5%で契約した人が、現在の金利1.8%で借り換えを行うと、総返済額を数百万円単位で減らせる場合があります。
借り換えを検討するタイミングの目安は、以下の3つです。
- 借入金利と現在の金利差が 0.5%以上 ある
- 返済期間が 10年以上 残っている
- 残高が 1,000万円以上 ある
これらの条件を満たす場合、借り換えのメリットが得やすいとされています。
また、変動金利で借りている人が金利上昇を懸念してフラット35へ借り換えるケースも増えています。
今後の金利上昇リスクを抑え、「固定で安定した返済を続けたい」という人には、このタイミングでの乗り換えは有効な選択肢です。
ただし、借り換えには登記費用や事務手数料などの諸費用が発生するため、シミュレーションを行って実質的なメリットを確認することが大切です。
「安心を買う」ならフラット35という選択
フラット35は、将来の金利上昇リスクを避けたい人に最も適した住宅ローンです。借入時に金利が固定されるため、35年間の返済額が変わらず、経済状況や政策金利の影響を受けません。
「今後金利が上がったらどうしよう」という不安を感じている人にとって、フラット35は“安心を買う”選択肢といえます。
もちろん、フラット35には「初期金利が高い」「審査に時間がかかる」などのデメリットもあります。
しかし、それらを理解したうえで選択すれば、長期的に安定した返済を続けられる強みがあります。特に、家族の将来設計や教育費など、長期にわたる家計の見通しを立てたい人にとって、返済額が一定であることは大きな安心材料になります。
最も大切なのは、自分のライフプランに合った金利タイプを選ぶことです。「とにかく金利を抑えたい」なら変動金利、「安心を重視したい」ならフラット35というように、目的に応じた選択が住宅ローン成功のカギです。
ローンは“借りる”だけでなく“安心して返す”ための仕組み。あなたにとって最適な金利タイプを見極め、無理のない返済計画で理想のマイホームを実現しましょう。